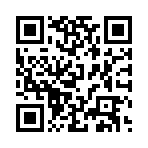2012年01月15日
バッロクチェロ 公開レッスン
バロックチェロ(415Hz)でのレッスンです。
ヴィヴァルディのソナタ変ロ長調(Rv45)で受けました。
ヴァージナルは室内楽仲間のYさんに付き合ってもらいました。

講師の西沢央子さんは一緒に通奏低音をひきながら
「(バロックボウでは)筆で書く時のように、起筆-運筆-はね-かすれ、濃淡などいろいろな音色を」
「モダンの弓は常に一定の音を出せるようになっている。言わばシャープペンシル」
「(2楽章の)Allegroは強拍/弱拍差をはっきり。強拍は弓のスピードを・・・・」
など具体的でイメージに満ちた指導をして下さり、いちいち納得でした。
前日は県立芸術劇場のコンサート”J.S.バッハの魅力”に出演されて、素敵な通奏低音を聴かせてくれました。
ガット弦とバロックボウの組み合わせで弾くと、バッハの無伴奏組曲がとても身近な曲になります。
マグダレーナ・バッハの筆写譜のスラーの位置では(いろいろ議論はあるものの・・)現代チェロで弾こうとするとギクシャクしたり、意味不明だったりしていました。19世紀以来の大家的解釈にドップリ染まっているからかもしれませんが。
バロック楽器ではごく自然に弾けるし、力まないでよい。
しばらくのめり込みそうです。
ヴィヴァルディのソナタ変ロ長調(Rv45)で受けました。
ヴァージナルは室内楽仲間のYさんに付き合ってもらいました。

講師の西沢央子さんは一緒に通奏低音をひきながら
「(バロックボウでは)筆で書く時のように、起筆-運筆-はね-かすれ、濃淡などいろいろな音色を」
「モダンの弓は常に一定の音を出せるようになっている。言わばシャープペンシル」
「(2楽章の)Allegroは強拍/弱拍差をはっきり。強拍は弓のスピードを・・・・」
など具体的でイメージに満ちた指導をして下さり、いちいち納得でした。
前日は県立芸術劇場のコンサート”J.S.バッハの魅力”に出演されて、素敵な通奏低音を聴かせてくれました。
ガット弦とバロックボウの組み合わせで弾くと、バッハの無伴奏組曲がとても身近な曲になります。
マグダレーナ・バッハの筆写譜のスラーの位置では(いろいろ議論はあるものの・・)現代チェロで弾こうとするとギクシャクしたり、意味不明だったりしていました。19世紀以来の大家的解釈にドップリ染まっているからかもしれませんが。
バロック楽器ではごく自然に弾けるし、力まないでよい。
しばらくのめり込みそうです。
Posted by tanuki at 13:01│Comments(0)
│チェロ