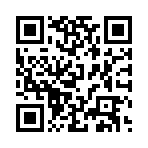2012年01月19日
グスタフ・レオンハルト
亡くなったんですね。
1970年ころのLPの冒頭、ゲオルク・ベームのアルマンド(?)の印象は忘れられません。
奥行きのあるしみじみとした響きが今でも耳に残っています。
楽器についても'60年代まではノイペルト、スペアハーケなどの「モダンチェンバロ」が普通で、それをヘルムート・ヴァルハとかカール・リヒターのLPで聴いていました。
それはそれでとても素敵でしたが、70年ころから国内でもポツポツ見られるようになった「ヒストリカル」な楽器の響きはとても新鮮でした。
製作家マルチン・スコヴロネックの名前はレオンハルトのLPで初めて知りました。
40年越しと言うことになります。
合掌
1970年ころのLPの冒頭、ゲオルク・ベームのアルマンド(?)の印象は忘れられません。
奥行きのあるしみじみとした響きが今でも耳に残っています。
楽器についても'60年代まではノイペルト、スペアハーケなどの「モダンチェンバロ」が普通で、それをヘルムート・ヴァルハとかカール・リヒターのLPで聴いていました。
それはそれでとても素敵でしたが、70年ころから国内でもポツポツ見られるようになった「ヒストリカル」な楽器の響きはとても新鮮でした。
製作家マルチン・スコヴロネックの名前はレオンハルトのLPで初めて知りました。
40年越しと言うことになります。
合掌
2012年01月15日
バッロクチェロ 公開レッスン
バロックチェロ(415Hz)でのレッスンです。
ヴィヴァルディのソナタ変ロ長調(Rv45)で受けました。
ヴァージナルは室内楽仲間のYさんに付き合ってもらいました。

講師の西沢央子さんは一緒に通奏低音をひきながら
「(バロックボウでは)筆で書く時のように、起筆-運筆-はね-かすれ、濃淡などいろいろな音色を」
「モダンの弓は常に一定の音を出せるようになっている。言わばシャープペンシル」
「(2楽章の)Allegroは強拍/弱拍差をはっきり。強拍は弓のスピードを・・・・」
など具体的でイメージに満ちた指導をして下さり、いちいち納得でした。
前日は県立芸術劇場のコンサート”J.S.バッハの魅力”に出演されて、素敵な通奏低音を聴かせてくれました。
ガット弦とバロックボウの組み合わせで弾くと、バッハの無伴奏組曲がとても身近な曲になります。
マグダレーナ・バッハの筆写譜のスラーの位置では(いろいろ議論はあるものの・・)現代チェロで弾こうとするとギクシャクしたり、意味不明だったりしていました。19世紀以来の大家的解釈にドップリ染まっているからかもしれませんが。
バロック楽器ではごく自然に弾けるし、力まないでよい。
しばらくのめり込みそうです。
ヴィヴァルディのソナタ変ロ長調(Rv45)で受けました。
ヴァージナルは室内楽仲間のYさんに付き合ってもらいました。

講師の西沢央子さんは一緒に通奏低音をひきながら
「(バロックボウでは)筆で書く時のように、起筆-運筆-はね-かすれ、濃淡などいろいろな音色を」
「モダンの弓は常に一定の音を出せるようになっている。言わばシャープペンシル」
「(2楽章の)Allegroは強拍/弱拍差をはっきり。強拍は弓のスピードを・・・・」
など具体的でイメージに満ちた指導をして下さり、いちいち納得でした。
前日は県立芸術劇場のコンサート”J.S.バッハの魅力”に出演されて、素敵な通奏低音を聴かせてくれました。
ガット弦とバロックボウの組み合わせで弾くと、バッハの無伴奏組曲がとても身近な曲になります。
マグダレーナ・バッハの筆写譜のスラーの位置では(いろいろ議論はあるものの・・)現代チェロで弾こうとするとギクシャクしたり、意味不明だったりしていました。19世紀以来の大家的解釈にドップリ染まっているからかもしれませんが。
バロック楽器ではごく自然に弾けるし、力まないでよい。
しばらくのめり込みそうです。
2012年01月01日
Toothing Plane (ギザ溝鉋?)
あけましておめでとうございます。
マルチン・スコヴロネック(Martin Skowroneck)が言うには、
接着面に"toothing"することが古くから行われてきた。 "Toothing Plane" で細かい溝を付けると余った接着剤の逃げ場になり、また、工程上のミスを緩和してくれる-ミスを完璧に防ぐことは出来ないからね-
嬉しいご発言

余談だがこの人世界の名工なのに、こうした現場的で気取らないアプローチが満ちていて読んでいるとつい膝を痛くなるほど叩いてしまいます。
この本です、参考まで:
http://www.amazon.co.jp/Cembalobau-Martin-Skowroneck/dp/3932275586/ref=sr_1_1?s=english-books&ie=UTF8&qid=1325392235&sr=1-1
それで、ギザ溝鉋(?)を探し回りました。欧米ではポツポツと使われているようです。
接着面の溝入れだけでなく、複雑な木目を仕上げる前処理に使って逆目を防ぐと言う使い方が多いようです。
参考:http://anthonyhaycabinetmaker.wordpress.com/2011/01/29/the-toothing-plane-a-tool-of-our-time/
ところが国内には何処にも無い!
日本鉋では名人にかかると大概の木目は削れてしまうので必要なかったのだろうか?
探し回った揚げ句、千葉のM先輩が貸してくれました。
アイアン(刃)だけを入手したそうで、スタンレーのブロックプレーンに合う仕様になってます。

SPF材の端材を削ってみるとWEBで見たとおりの削り屑が出ました。